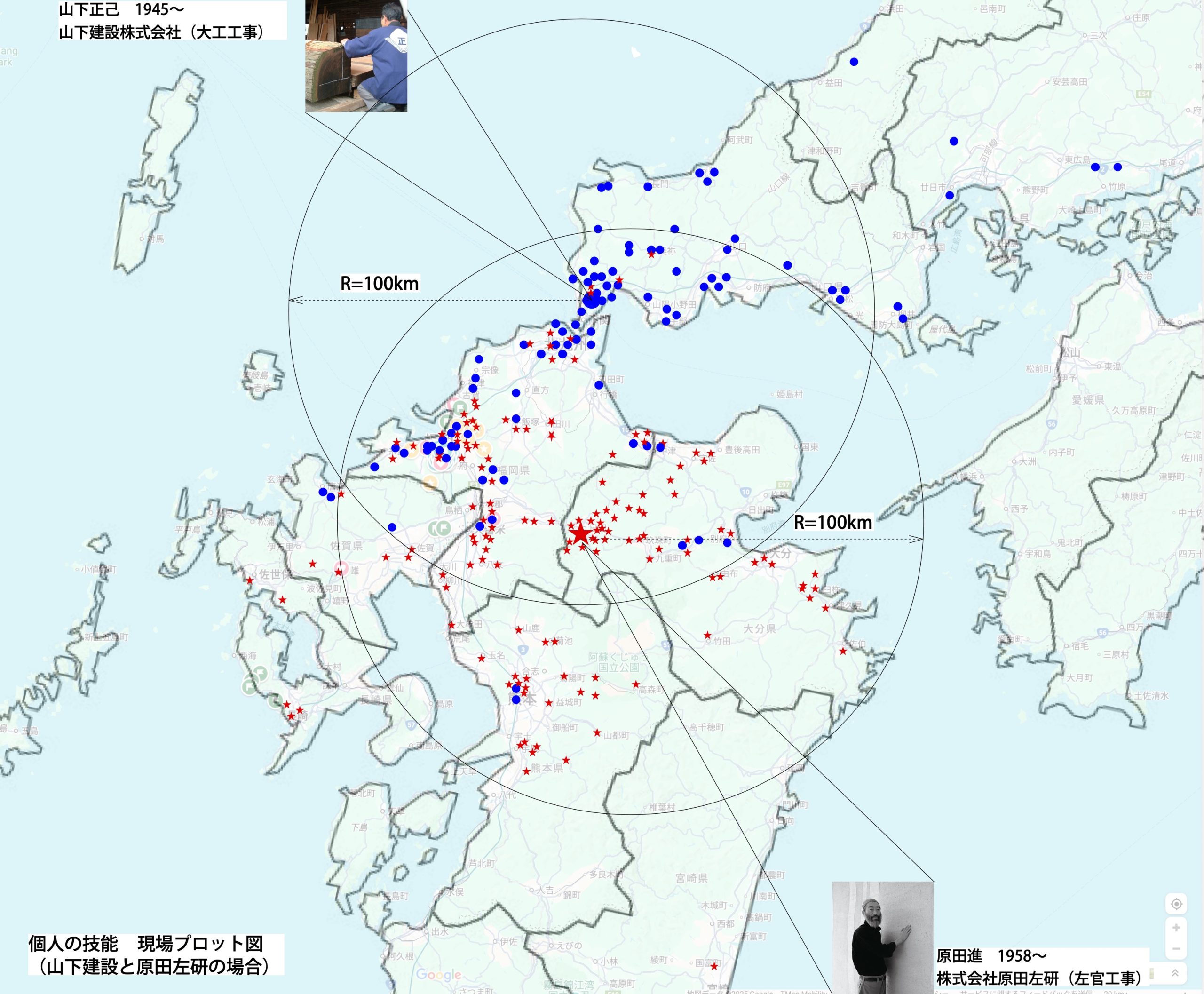先日、面白い現代音楽を聴きにアクロス円形ホールに出向くことがあった。「自然真営祭」というピアニスト河合拓始(かわいたくじ)さん率いる楽団の皆さんによる、自然真営道/安藤昌益(1703-1762)の文章に曲をつけた戯曲?劇?コンサート?である。安藤昌益は、「自然の中での労働に全ての真理がある」とした江戸時代の医師、思想家、哲学者である。彼の思想には、陰陽五行の「五行」が下敷きになっているらしく、言葉と身体の関係とか、口や鼻との関係など、やはり相生と相克の関係論で説明されていた。(正確には、彼は五行のうち「土」を別格に持ち上げて、他を4行とした、という)音楽の歌詞といえば、特に歌謡曲などは、恋心などの個人の心内を歌ったものが大半だが、より概念的な思想の類を楽曲として表現するというのは、なるほど深いと思った。河合さんがその思想の文言につけた曲がまたとても良くて、聞き入った。だからか?にもかかわらずか?私は音楽を聴くときはあまり歌詞を追わないので、肝心の昌益の言葉は、ほとんど馬耳東風となってしまった。アナーキストとされる昌益の本性は骨太だから、そのくらいの聴き方の方がもしかしたらちょうどよかった、ということにならないだろうか。河合さんによる和音の進行がここちよすぎた、ということにでもしておこう。
先日、面白い現代音楽を聴きにアクロス円形ホールに出向くことがあった。「自然真営祭」というピアニスト河合拓始(かわいたくじ)さん率いる楽団の皆さんによる、自然真営道/安藤昌益(1703-1762)の文章に曲をつけた戯曲?劇?コンサート?である。安藤昌益は、「自然の中での労働に全ての真理がある」とした江戸時代の医師、思想家、哲学者である。彼の思想には、陰陽五行の「五行」が下敷きになっているらしく、言葉と身体の関係とか、口や鼻との関係など、やはり相生と相克の関係論で説明されていた。(正確には、彼は五行のうち「土」を別格に持ち上げて、他を4行とした、という)音楽の歌詞といえば、特に歌謡曲などは、恋心などの個人の心内を歌ったものが大半だが、より概念的な思想の類を楽曲として表現するというのは、なるほど深いと思った。河合さんがその思想の文言につけた曲がまたとても良くて、聞き入った。だからか?にもかかわらずか?私は音楽を聴くときはあまり歌詞を追わないので、肝心の昌益の言葉は、ほとんど馬耳東風となってしまった。アナーキストとされる昌益の本性は骨太だから、そのくらいの聴き方の方がもしかしたらちょうどよかった、ということにならないだろうか。河合さんによる和音の進行がここちよすぎた、ということにでもしておこう。
このコンサートの2日前の日曜日、IARP本部講師ヨガ講習会にて、やはり人間の身体と五行の話だったことを思い出した。五行とは、世界のあらゆる現象や仕組みを木・火・土・金・水の五つの要素と関係性で捉える、古代中国の思想体系。古代中国とはいつかというと、「黄帝内経」という中国の医学文献の中で、身体と自然と宇宙を陰陽五行により説明されているということで、黄帝(紀元前27世紀)まで遡るということになる。ちなみにchatGTPによれば、黄帝は実在する人物ではない、あるいは一人の実在する人物ではない、とかなり不在説寄りだった。が、私は、この場合の彼(chatGTP)はクラウド上の情報に惑わされているな、と思った。実在しなければユンケル黄帝液はどうなる?というような心配はしないが、でもこう言う時は、聖徳太子とか神功皇后とか、神代の天皇とか、著名人物ほど不在説が伴うという法則を差っ引いて考えるようにしている。実在が科学的に確認されてないなら、事実が確認されていない、という事実だけを踏まえておけば、あとは彼らが言った、行ったとされることを素直に受け止めればいい、ということにしている。(そういう傑物を作り話として作り上げたとしたら、それも尊いことだと思う)
陰陽五行の五行は、五行相生(そうせい)と五行相克で成り立っていて、相生は、たとえば「木は燃えて火を生む」というふうに、互いに生み合う関係。そして相克は、たとえば「木は土の養分を奪う」というように、互いを抑制する関係。この対照的な関係性が両立していることによって、全体が成り立っているというシステム論というふうに受け止めた。
そして、聞き入ったのは、この五行が人間の身体の営みの中に仕組まれているという。図にあるように、『水』は、腎臓や膀胱などの人間の身体の水分を浄化する役割のことを指していて、それが活発に働く時間が夜の21時から1時の間と決まっている?という。『木』=肝臓/胆嚢 は、体外から入ってきたものを解毒する役目だが、それらは『水』の刻の次、夜中の3時から朝の7時の間に、この役割が活発になるという。『水』~『木』の刻、つまり、日が暮れている間にこれらの臓器が体の回復を施すから、その時間は当然ながらきちんと休んでいなさい、となる。そしてこの時間は、食べ物を消化する時間となるべく重ならないように、寝る前の3時間は飲食をしないように、となる。ずばり、夕食は18時に食べ終わっているべき、のようである。お寺の食事は今でこそ3食だが、かつては、2食、1食、つまり夕食は食べないものだったらしいから、これらの理にかなっている。
自分も、時々夕食抜きをやるが、これがとても身体にいいことを実感している。睡眠の質もいいし、翌日のお腹の感じもスッキリしていて快適である。「空腹はなぜいいか」石原 結實(2015/php文庫)にも、16時間断食の計り知れない効用が述べられていた。 現代のお寺がなぜ3食になったかは、多分、世の中の3食の習慣に従っているからではないか、という天台宗の雲水でもあるヨガの先生のお話しだった。確かに問題は、我が身の周りとの社会生活上のギャップである。私は夕食抜き(と決めた)日に宴会のお誘いをいただくと、「その日は宗教上の理由(ラマダン)で、出席できません」と半分冗談、半分ほんとのことを言って、失礼したりする。心身をすっきりとさせるべき予定の前日は、飲酒諸共夕食を抜く、の絶好の機会にしている。
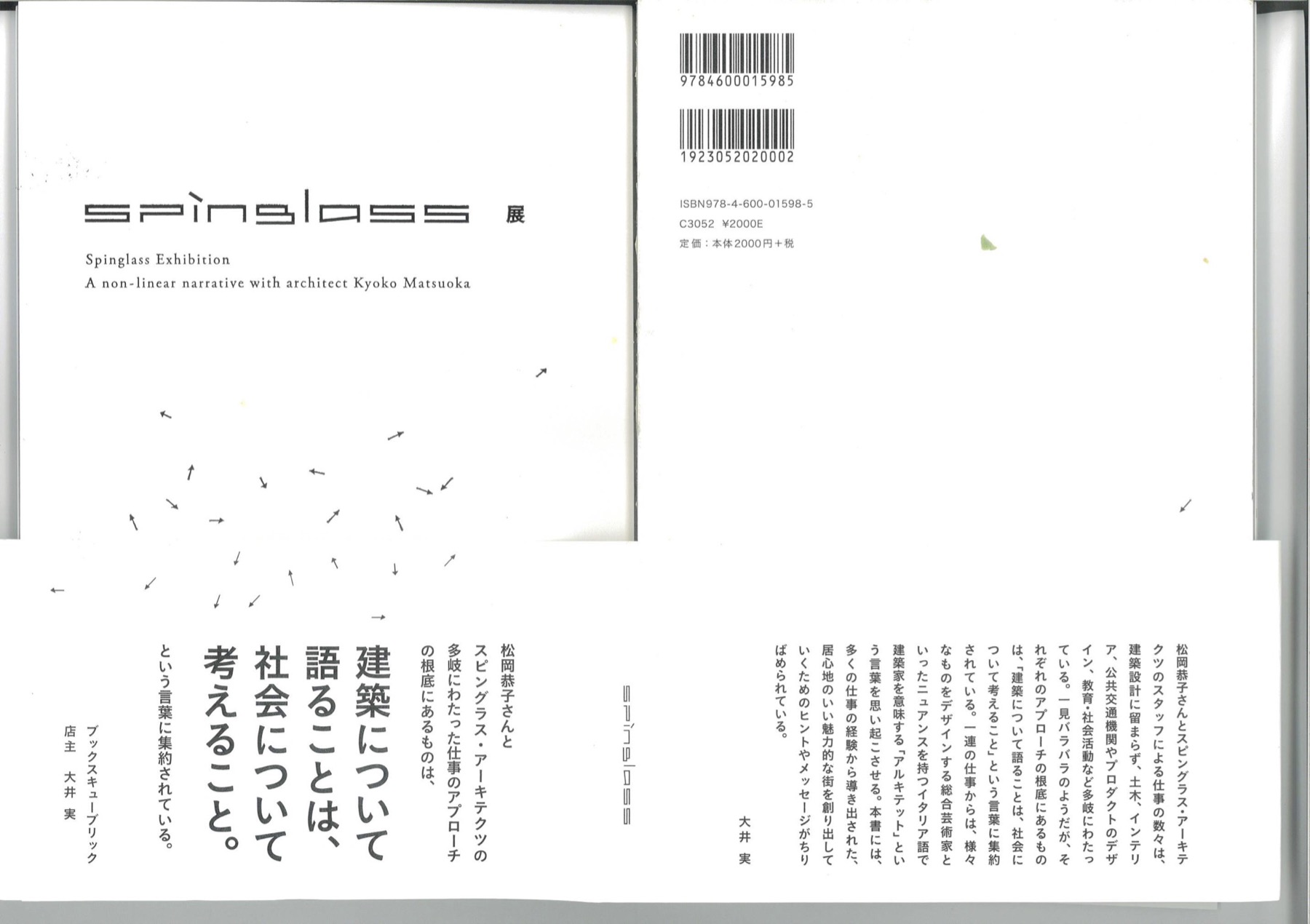 「spinglass exhibition」を恵贈いただく。展覧会のサブタイトルに、「非線形の物語」とある。非線形とは、本書末の鼎談で松岡恭子さんが述べられているとおり、「方程式があって、それに従い、自動的に、ルールに従って、結論が導かれるのとは異なり、結論に直結しない増幅性や複雑性を意味する語である。」この意味が、スピングラスという事務所名として結実している。「スピングラスとは、電子スピンがバラバラな方向を向いたまま凍結された物質の状態のことです。バラバラなためにスピンの間にフラストレーションが生じていますが、凍結されたことで時間的に秩序をもった状態であると考えるそうです。物質で例えるなら準安定状態の黒曜石やガラスのようなものだと説明を受けました」
「spinglass exhibition」を恵贈いただく。展覧会のサブタイトルに、「非線形の物語」とある。非線形とは、本書末の鼎談で松岡恭子さんが述べられているとおり、「方程式があって、それに従い、自動的に、ルールに従って、結論が導かれるのとは異なり、結論に直結しない増幅性や複雑性を意味する語である。」この意味が、スピングラスという事務所名として結実している。「スピングラスとは、電子スピンがバラバラな方向を向いたまま凍結された物質の状態のことです。バラバラなためにスピンの間にフラストレーションが生じていますが、凍結されたことで時間的に秩序をもった状態であると考えるそうです。物質で例えるなら準安定状態の黒曜石やガラスのようなものだと説明を受けました」